アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:鹿児島市立伊敷中学校
教科等:1年社会科(平成29年2月)
単元名:東アジア世界との関わりと社会の変動
対話を通して考えを深める力を育成したい
 見通しを持つ
見通しを持つ 協働して課題解決する
協働して課題解決する 知識や技能を概念化する
知識や技能を概念化する
実践の背景
- 実践校は研究校としての使命を担い、時代の要請に応じた研究・実践を重ね、その成果等を多くの学校へ公開しています。
- 「新しい時代を切り拓く資質・能力を身に付けた生徒の育成」という研究主題を掲げ、教科横断的な視点から考えた学校で目指す資質・能力である「課題発見力」「情報活用力」「論理的思考力」「協働する力」「メタ認知」の育成に向け、研究を進めています。
- 研究主題に迫るために、「教科の本質に迫る深い学びにおける生徒の姿の具体化」「考えを広げ深める手立ての工夫」「学習プロセスを見通し・振り返る活動の充実」の視点から、生徒の学びに寄り添った授業の実現を目指しています。
授業改善のアプローチ
- 問題解決的な学習において、試行錯誤する生徒の思考の流れを「気付き」「納得」「意志」というキーワードから予想することによって、思考を深化、拡張する支援を計画しました。
- 自らの生活経験や既習事項から気付いた課題を他者と共に解決する学びを通して、納得を伴った理解に基づき、学んだことを今後の学習や生活に生かそうとする意志を育む授業を目指しました。
- 主体的な学びの実現を目指し、見通しの場面で問いに対する自らの考えを表出したり、振り返りの場面で自らの考えの変化について気付いたりする場面を設定しました。
- 未知の情報と出会い、判断を迫ったり、考えを揺さぶったりする場面を設定することで、対話を通しながら考えが広がったり深まったりする授業を展開しました。
- 生徒の深い理解に至った状態を「多面的・多角的な視点を踏まえた上で、論理的に自分の考えを再構成し、学習課題や現実的な課題に対して最適解を提案することができる状態」と考え、深い理解に至った生徒の姿を想定しながら、単元や授業を構成しました。
単元づくりのポイント
目標
- 武家政治の展開や経済の発達と社会の変化、東アジア世界とのつながり、室町文化についての学習に関心を持ち、意欲的に追究しようとする。
【社会的事象への関心・意欲・態度】 -
元寇や日明貿易が日本の政治や社会に与えた影響、都市や農村における自治的な仕組みの成立、応仁の乱後の社会的な変動、武士や民衆の活力を背景にした新しい文化などについて多面的・多角的に考察し、その過程や結果を適切に表現することができる。
【社会的な思考・判断・表現】 - 武家政治と社会の変化、室町文化に関する史料、図版、年表、歴史地図などのさまざまな資料を活用し、必要な情報を読み取ることができる。
【資料活用の技能】 -
元寇や日明貿易が日本の政治や社会に与えた影響、都市や農村における自治的な仕組みの成立、応仁の乱後の社会的な変動、武士や民衆の活力を背景にした新しい文化などについて、相互の関連性を含めて理解し、その知識を身に付けることができる。
【社会的事象についての知識・理解】
展開
- 1 東アジア世界の変化が鎌倉幕府の滅亡に与えた影響を理解する(2時間)
-
- 元寇が鎌倉幕府に与えた影響を考える
- 建武の新政から南北朝の争乱に至る経緯を理解し、室町幕府の仕組みを捉える
- 2 室町時代の政治面・外交面・社会面・文化面において特色を理解する(5時間)
-
- 明・朝鮮国・日本の結びつきや、琉球王国・蝦夷地の人々との関わりについて理解する
- 産業の発達が、民衆の生活に与えた影響を考える
- 応仁の乱や下剋上の風潮から、戦国大名の登場を理解することができる
- 室町文化の特色を考えたり、現在に結びつくものがみられることに気付いたりする
- 応仁の乱について多面的・多角的に考察することができる (本時)
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
- 応仁の乱が11年に渡って続いた理由を、政治面、外交面、社会面、文化面との関連から考察することを通して、室町時代の特色を理解することができる。
授業場面より
-
①なぜ11年も続いたのだろう?

学習課題を把握する場面です。教師は、応仁の乱の状況を表した絵巻を電子黒板に示しました。そして、これまで学習した他の乱を振り返りながら、「なぜ応仁の乱は11年間も続いたのだろう」と、その期間に焦点をあてた問いを投げかけました。生徒は、前時までに、武士が台頭してきたことや、武家政権の支配が全国に広まってきた事実について学習していましたが、11年という期間が、他の乱と比べて長いものであったという新たな情報に驚き、興味を抱き、その理由を改めて考えたくなりました。
-
②他にも理由がありそうだ!
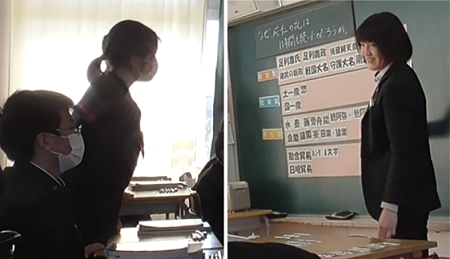
課題の解決に向け見通しをもつ場面です。教師は、本単元で学んだことを、既習のキーワードを通して振り返りたいと考え、キーワードの発表を促しました。そして、次々に発表する生徒の発言を政治、外交、社会、文化のカテゴリーで分類していきました。生徒は、分類されたキーワードを見ながら、室町時代の特徴を整理しながら確認していきます。同時に、応仁の乱の背景を、政権争いを中心とする政治的な理由からだけではなく、多面的な視点から迫る必要性に気付いていきました。
-
③もっと調べてみよう!
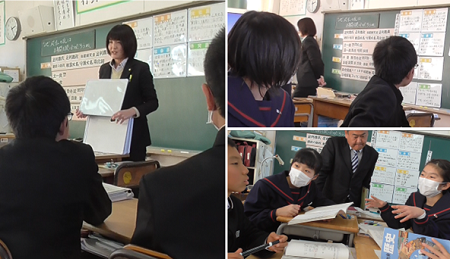
グループで課題について考える場面です。教師は、グループで前時にまとめた室町時代の政治、外交、社会、文化の特徴を黒板に示し、4つの視点を関連付け、応仁の乱の背景を考えるように促しました。生徒は、それぞれの特徴についてさらに詳しく調べ始めます。そして、資料集や既習事項をまとめたノート等を示しつつ、互いの考えを伝え合います。室町時代の変遷を、政権の動きや日本と東アジアとの関係、民衆の生活の変化から捉えるなど、複数の視点から当時の背景を理解することを通し、課題解決に向かう姿が見られました。
-
④いろんなことが関係しているぞ!

課題を解決し、自らの学びを振り返る場面です。教師は、各グループで自分たちの考えを伝える人と他のグループの考えを聞く人に分かれて意見を交流するように促しました。生徒は、他のグループとの交流を通してそれぞれが収集した情報を伝え合った後、自らの考えをまとめます。混迷した政権、民衆による自治意識の進歩、守護大名の出現など、歴史的事実の関連を理解しながら、その中で生まれた不安定な時代背景が、応仁の乱の長期化の要因であり、同時に、応仁の乱の影響が不安定な時代背景につながったという相互の関係に納得することができました。
報告者:研修協力員 窪

