アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:横浜市立日枝小学校
教科等:4年総合的な学習の時間(平成28年10月)
単元名:太陽パワーで省エネ生活
活動や体験を通して課題解決に向かう力を育成したい
 見通しを持つ
見通しを持つ 協働して課題解決する
協働して課題解決する 思考して問い続ける
思考して問い続ける
実践の背景
- 総合的な学習の時間や生活科を中心に、教科・道徳・特別活動等の内容を関連付け教育課程の編成を図ることで、子供たちの思いや願いを学習に取り込み、子供が主体の学校生活を創出しようとしています。
- 総合的な学習の時間や生活科の時間に、それらと関連する教科等(教科・道徳・特別活動等)の時数を加え、「総合活動」と名付けた学びを実践しています。
- 「体験を通して生きて働く『知』を創造する学びを求めて」を研究主題に設定し、活動や体験を重視した「総合活動」を通じて、子供が主体的に探究し、生きて働く「知」を身に付けていく学びの成立を目指しています。
授業改善のアプローチ
- 子供の生活の中から生まれた問題を解決する過程で身に付けた力が、よりよい生き方を求めていく力になるという考えに基づき、子供の生活に密着した材を取り上げた単元の構成に取り組んでいます。
- 教科等の学習内容や活動に関連をもたせることによって、それぞれの場面で育まれる意欲や能力等が他の場面に波及していくことを願い、教科等の目標や内容の効果的な関連を図った単元の展開をしています。
- 目標の明確化を図ると共に、目標を実現している子供の具体を想定しながら、発問や板書の工夫、活動形態や場の工夫など、意図的かつ柔軟に手立てを講じています。
単元づくりのポイント
目標
- 震災が起きたときの生活を想像しながら、非常食を試したり、ソーラークッキングを行ったり、発電について調べたりする活動を通して、水や電気、ガスをいつでも使うことができる日常生活のありがたさを実感する。
- エネルギーの大切さや再生可能エネルギーの可能性に気付き、「省エネ」に取り組んでいこうとする態度を育てる。
展開
- 1 非常食について調べてみよう(10時間)
-
- 避難生活を想像して、自分たちでも体験する計画を立てる。
- 非常食を作って、食べてみる。
- 活動を振り返って、次の活動を考えよう。
- 2 エネルギーについて調べよう(15時間)
-
- ソーラーパネルを探す。
- 発電の仕組みを調べる。
- 風力、火力発電所を見学する。
- 身近なエコを調べて、実践する。
- 3 ソーラークッキングに挑戦しよう(30時間)
-
- ソーラークッカーを作って料理をする。(本時)
- 4-3オリジナルエコクッキングに挑戦しよう。
- 活動を振り返り、新たに取り組む活動を考える。
- 4 エネルギーの大切さを広めよう(20時間)
-
- 日枝っ子まつりの計画を立てる。
- 日枝っ子まつりに向けた準備を進める。
- 日枝っ子まつりで自分たちの活動を伝える。
- 一年間の活動を振り返る。
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
- 自分たちが作ったソーラークッカーでご飯を炊いた活動を振り返り、それぞれのグループが作ったソーラークッカーを見合う活動を通して、効率よく太陽の熱を集めるためにはどのように改良したらよいか考え、次のソーラークッカーの製作に向けての課題を明確にもつことができる。
授業場面より
-
①あきらめない!

自作のソーラークッカーを使ってご飯を炊いた前時の学習を振り返る場面です。教師は既に生徒の振り返りシートでうまくいかなかったことを把握しています。そのことを踏まえて「1回目、お米どうだった?」と、2回目の挑戦があるという含みをもたせ、問いかけました。児童は「固かった」と答えながら、初めての調理が失敗に終わった、学びについて口々に語り出します。「(製作を)あきらめない!」と発言する姿に、課題の解決に向けて、粘り強く取り組もうとする気持ちが表れていました。
-
②なぜ失敗したのだろう?
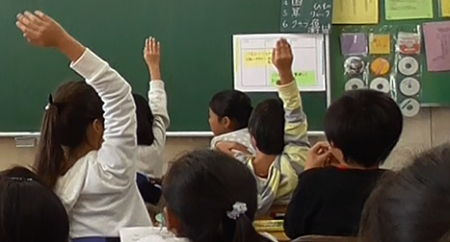
全体で考えを交流する場面です。教師は、ソーラークッカーの改良に向けて、まず失敗の原因だと考えることを発表するように促しました。そして、最初に「太陽があたっていなかった」と発表した児童の考えに共感を示します。このやりとりをきっかけに、他の児童も太陽の熱を集めることができなかったという観点から、ソーラークッカーの形、大きさ、材質、設置した場所など失敗の原因と考えられることを発表します。失敗の原因を明らかにすることを通して課題の解決に向かいます。
-
③比べてみよう!

課題を解決するための見通しを考える場面です。失敗の原因に関する意見交換を受け、教師は「どうやって解決する?」と問いかけました。ある児童が、改良のヒントを見付けるために、学校にある実物で試してみることを提案しました。さらに他の児童が「付け加えて」と言って、「学校で使っている容器と自作の容器で試して、違いを比べてみてはどうだろうか」という新たな提案を発表します。対話を通して考えを交流しながら、全員で改良に向けた取組を探っていく姿が見られました。
-
④アドバイスをもらおう!

課題解決の見通しを整理する場面です。教師は、次時に実物を見学したり、専門家の方からアドバイスをもらったりする機会を設定していると伝えます。設置する場所によって熱の集まり方に差が生じると考えたグループは、この点について専門家からアドバイスを受け、その後、製作を再開する計画を立てました。他のグループも太陽の熱を効率よく集めるという視点から改良に向けた取組を整理していきます。このような学びを通して、課題解決に向け、思考して問い続ける姿を見ることができました。
報告者:研修協力員 窪

