アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:我孫子市立我孫子第一小学校
教科等:6年国語科(平成29年11月)
単元名:みんなで語ろう 誰もがいきいきとくらせる 夢いっぱい あびこプラン
対話を通してよりよい意見を形成し、伝える相手や目的を意識して表現する力を育成したい
 興味や関心を高める
興味や関心を高める 互いの考えを比較する
互いの考えを比較する 自分の思いや考えと結び付ける
自分の思いや考えと結び付ける
実践の背景
- 実践校は、創立145年の我孫子市で最も歴史のある伝統校です。
- 生きてはたらく表現力の育成を目指して行う学習活動を「総合表現活動」と定義し、教科等の横断的な視点で国語科と生活科・総合的な学習の時間を関連させた単元づくりを行っています。
- 研究主題を「児童が自ら課題を見出し、主体的・対話的に学ぶことができる国語科学習指導」とし、主体的・対話的に学べる手立てを工夫することで、実社会・実生活に生きてはたらく表現力を身に付けることを目標としています。
授業改善のアプローチ
- 教科等横断的な単元づくりにより、児童が主体的に取り組むことができる課題設定やどの教科・領域においても対話的に学ぶことができるよう児童の交流する力の育成に力を入れています。
- 「地域に誇りをもてる一小っ子」の育成を目指し、地域教材に注目した授業づくりに取り組んでいます。
- 最終的に児童が作成した未来の街づくりのプランを、本時授業を参観して頂いた我孫子市長に提出するなど、社会とつながる学びを目指しています。
- 校内研修体制を生かした綿密な年間研修計画を作成し、公開研究会などを通して、全職員がその都度振り返る機会を設定して、授業改善に取り組んでいます。
- 児童は市民へのインタビューや市役所の職員の施策説明などをもとに暮らしやすい街づくりに向けた様々なプランを考え、授業に臨みます。
- 本単元では、新学習指導要領への移行を見据えた単元づくりを試行しています。
単元づくりのポイント
目標
- 情報と情報との関係付けの仕方、図などによる語句と語句との関係の表し方を理解し、使うことができる。
(知識及び技能) - 互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、考えを広げたりまとめたりすることができる。
(思考力、判断力、表現力等) - 現在の我孫子についての問題意識をはっきりさせ、何を変えていけば未来の我孫子はよりよくなるか、各自がプランを明確にもち、討論に臨もうとする。
(国語の学びに向かう力) - 自分たちの街は、自分たちがよりよく変えていこうとする意識をもち、意見の違いを大切にしながら話し合い、考えを深めようとする。
(国語の学びに向かう力)
展開
- 1
-
教科書の例文を読み、パネルディスカッションを行う意味や目的を知る。
- 2
-
教科書の例文を読み、パネルディスカッションの進め方についてイメージをもつ。
- 3
-
論題を確認し、話し合う観点を出し合う。観点別グループに分かれ、論題についてグループ内で意見を交換したり、必要な資料について話し合ったりする。
- 4
-
パネルディスカッションの中で提示する資料を作成する。
- 5
-
役割を決めて、グループ内パネルディスカッションを行い、意見の組み立て方や資料の提示などをよりよいものにしようとする。
- 6
-
他のグループとのパネルディスカッションに向けて準備をする。
- 7
-
他のグループとパネルディスカッションを行い、自分や相手のよさに気付く。
- 8
-
パネルディスカッションを行う。(第1回)【本時】
- 9
-
パネルディスカッションを行う。(第2回)
- 10
-
パネルディスカッションを振り返り、自分の考えの深まりや変化をまとめる。
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
互いの立場や意図を明確にしながら計画的に話し合い、考えを広げたりまとめたりすることができる。
授業場面より
-
①班ごとにプランを発表する
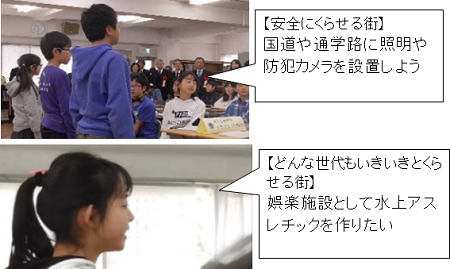
本時、児童は互いの立場や意図を明確にしながら行う話合いを通して、「未来の街づくりプラン」についての自分たちの考えを広げ深めていきます。発表者は自分たちの主張を効果的に伝えるため、絵や写真などをスクリーンに投影し、話の構成を工夫したり、聞き手の表情を見ながら、音量や速度、敬体や常体を使い分けたりするなど、前時までに学習したパネルディスカッションの内容を充実させるポイントを確認します。児童は、その場に応じた表現を心掛け、根拠を示しながら話すことができるよう習得した学習内容の活用・発揮を目指します。
-
②疑問に思ったことを聞いてみよう
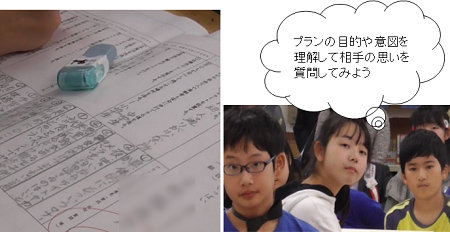
発表者の提案後の質問タイムでは「なぜその場所に照明や防犯カメラを設置するのか」という質問に対して、発表者は「夜は暗くて怖いし、交通事故や犯罪の発生率が高いというデータもあるから、国道や学校周辺の通学路に設置する」と回答しました。この班では、発表を通してデータや体験などの根拠を示し、話の構成を工夫することが、説得力のある説明につながると実感しました。
-
③聞き手からの意見により考えが深まる
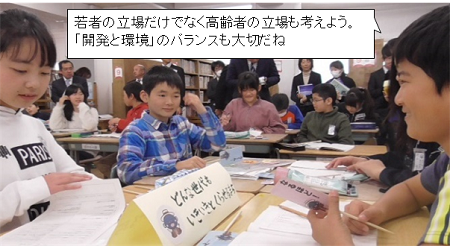
教師は聞き手の児童に自分の意見表明を促します。聞き手として「相手の意図をつかみながら聞く」ことの重要性を理解することや発表者が聞き手の意見を自分の評価につなげるだけでなく、自分のプランを再構成するためです。ある班では聞き手から「娯楽施設を作るのは良いが、環境に悪影響を与え、一部の人だけの楽しみになるのではないか」という指摘を受けました。班員は「若者の立場を中心に考えてしまい、『誰もが』という視点が弱かった」と分析しました。そして、みんなに納得してもらうためには、年代や価値観など多様な立場を意識した意見に再構築する必要性を感じたようでした。
-
④本時を振り返る
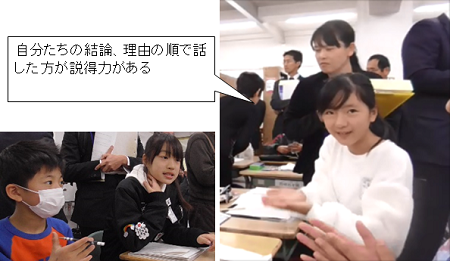
本時を振り返り、市長への提言に向けて、学級としての意見をまとめていきます。ある児童は、「みんなに納得してもらうためには、最初に結論を述べ、数値データや経験による根拠を示したり、具体例を示したりした方が説得力がある」と振り返りました。この学びを通して、児童は話し手として自分たちの考えを相手に的確に伝えるため「場に応じた適切な言葉遣い」を意識したり、聞き手として、話し手の意図を考慮しながら聞き、自分の意見と比べて考えをまとめようとする姿が見られました。
報告者:研修協力員 織田

