アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:徳島県立城ノ内中学校・高等学校
教科等:1年国語科(平成29年10月)
単元名:言葉の力について考えよう
「言葉」を通して互いの考えを深める力を育てたい
 見通しを持つ
見通しを持つ 互いの考えを比較する
互いの考えを比較する 自分の考えを形成する
自分の考えを形成する
実践の背景
- 実践校は中高一貫教育校で、生徒は県下のさまざまな小学校から集まっています。めざす生徒像は、次の通りです。
・社会貢献への自覚をもち、仲間と共に学び合い、向上していく人間性豊かな生徒
・多様な文化・価値観を尊重し、自己の考えや意思を表現できる国際性豊かな生徒
・科学技術に関心をもち、主体的に考え、追究することができる創造性豊かな生徒 - さらに、県の中等教育学校を牽引するリーディングハイスクールに指定されており、学力向上のための取組において、
・社会の平和と発展に貢献する人材となることをめざし,主体的に学ぶ力を伸ばす指導
・自己肯定感を高めることにつながる言語活動の充実
を研究テーマとし、授業改善に取り組んでいます。
授業改善のアプローチ
- これまでの授業で「空を見上げて」を読み、人の心を動かす言葉の力について考えています。また、互いの考えを深めることを目標に、「お気に入りの場所」についてのスピーチに取り組み、どうすれば相手に自分の言いたいことが伝わるか、内容の具体性や順序、話し方について考え、工夫しています。
- 授業者は、生徒の考えをどう活用するかを課題とし、ホワイトボードや付箋等、話合いをスムーズに行えるような工夫を考えています。
- ペアトークや班活動では活発に話し合うことはできていますが、話合いのテーマについて掘り下げて考え、意見を交流する力に課題があると捉えたため、授業改善に取り組んでいます。
単元づくりのポイント
目標
- 言葉がもつ価値に気付くとともに、言葉の力について考えを深めようとする。
【関心・意欲・態度】 - 話合いの方向を捉えて的確に話し、相手の言うことを注意して聞くことで自分の考えをまとめることができる。
【話すこと・聞くこと(オ)】 - 文章に表れているものの見方や考え方をとらえ,自分のものの見方や考え方を広くすること。
【読むこと(オ)】 - 事象や行為などを表す多様な語句について理解を深めることができる。
【伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項】
展開
第一次 「言葉の力」について考える
「空を見上げて」を読み、人の心を動かす言葉について考える(2時間)
第二次 「言葉の力」について、自分の考えをまとめる(1時間)
第三次 グループ・ディスカッションの進め方を知り、考えの広げ方、深め方を学ぶ
グループ・ディスカッションを実施する(1時間・本時)
第四次 学習を振り返り、話合いを経て深まった自分の考えをまとめる(1時間)
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
話合いの方向性を捉えて話し、相手の言うことを注意して聞いて自分の考えをまとめることができる。
授業場面より
-
①言葉にはどんな力があるのだろう
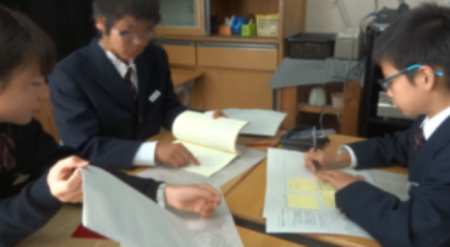
生徒は前時に「空を見上げて」という教材を読み、人々の心を動かした言葉の力について考えました。また、人の心を動かす言葉の例を教科書や本、新聞、インターネット等から探して書き留めていました。ある生徒は、テレビドラマの「毎日が100%じゃなくていい」というセリフを取り上げ、「心を閉ざしている子の心を動かすことができる」と言葉を通して人と人がつながることを感じたことを根拠にワークシートにまとめました。
教師は、生徒が考えている「言葉の力」について共有するためにグループディスカッションを設定しています。自分の考える「言葉の力」とその根拠をまとめるよう促すことで、生徒が自分の考えと根拠を明らかにした上でグループディスカッションに臨めるようにしました。 -
②質問の仕方って大事!
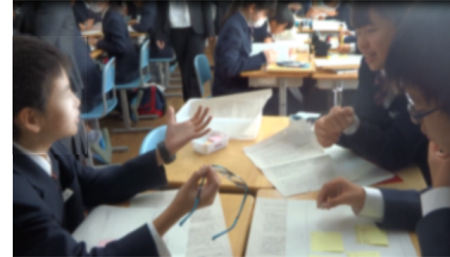
授業の前半では、話合いを深める質問の仕方を身に付けられるように模擬的なグループ・ディスカッションが行われました。
教師は、モデル対話を台本として用意するとともに、「司会者」と「発表者」と「記述者」という役割を分担し、順番に回していくことで、すべての生徒が対話に関わることができるようにしました。さらに、実際に模擬的なグループ・ディスカッションを行った後、話合いの内容を深める質問にはどのようなものがあるか台本の本文に線を引くよう促しました。
生徒は質問を吟味することで、後半で行うグループ・ディスカッションで、話を深めるためにどのような質問をすればよいのか見通しを持つことができました。 -
③いろんな「言葉の力」があるんだな
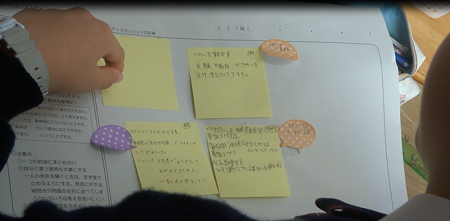
授業の後半は、「言葉の力」をテーマにしたグループ・ディスカッションです。生徒は、ワークシートに自分の考えた「言葉の力」とその根拠をまとめています。
教師は数種類の付箋を用意することで、生徒が付箋をワークシート上に貼り付け、互いの考えを比較できるようにしました。
生徒が考えた「言葉の力」とその根拠が貼り出されました。また、授業の前半で共有した話合いを深めるための質問の仕方を活用し、より詳しく聞き取りたいことを話し合うなど、ワークシート上にグループの仲間と考えた「言葉の力」が整理されていきました。 -
④言葉の力について、もう一度考えてみよう
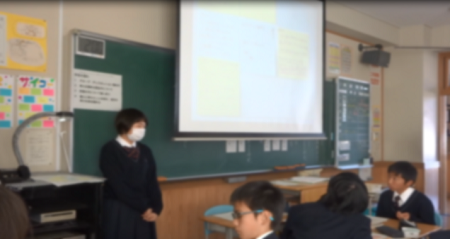
まとめの時間です。教師はグループ・ディスカッションの記録をワークシートへ記述するように促します。
ある生徒は「自分は言葉の力が人を動かして変えるという捉え方しかしていませんでしたが、話合いで表現する力と伝える力についても捉えている人がいて、考えが加わりました」と記述し、発表しました。多様な考えを持つ他者と比較・交流したことによって、自らの考えの変容を自覚した姿と捉えられます。次時には、自分の考えを本時の話合いを踏まえて再度まとめていきます。
報告者:研修協力員 木下

