アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:福岡県立鞍手高等学校
多面的・多角的に歴史的事象を考察し、その結果を表現する力を養いたい
 粘り強く取り組む
粘り強く取り組む 協働して課題解決する
協働して課題解決する 知識・技能を活用する
知識・技能を活用する
実践の背景
- 実践校は、創立百周年を迎えた地域の伝統校です。普通科、普通科人間文科コース、理数科を有し、卒業後は大学及び専門学校に進学する生徒がほとんどです。
- SSH及びSGHの指定を受け、科学技術イノベーションを担う人材、グローバルな視点で地域の発展や課題解決のために貢献しようとするグローバルリーダーの育成を目指しています。
- 50年来の校是である、「たくましき前進者」を再定義し、7つの「力」で表しました。その「力」の育成のために、課題研究や研修の充実、主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善に取り組んでいます。
- 主体的に学習に取り組む姿勢をもつ生徒が多い一方で、資料から読み取った内容を基に推測すること、多面的・多角的に考察し、考察した内容を表現することに課題を感じている生徒もいます。
授業改善のアプローチ
- 歴史的事象を多面的・多角的に考察できるよう、学習テーマを設定すると共に、単元を「課題把握」「課題追究」「課題解決」の三つで構成し、資料を読み取る活動やグループでの意見交換を位置付けます。
- 資料を読み取る活動やグループでの意見交換が上手く進むように、活動前に手順や評価項目を示します。また、活動中に生徒の発言を踏まえて状況に応じた問いかけを行います。
- グループでのプレゼンスライドを用いた発表、500字以上の論述など自己の考えを形成する学びを大切にし、知の精緻化を図るとともに表現力の向上を目指します。
単元づくりのポイント
目標
- オアシス都市や遊牧国家の動向及び中華帝国との関係を意欲的な態度で追究することができる。
【関心・意欲・態度】 - 資料を活用し、遊牧国家の動向及び中華帝国との関係を現代の国際関係に照らして複数の側面、関連・変化や立場から追究、考察し、その過程や結果を論理的に表現することができる。
【思考・判断・表現】 - 遊牧国家の動向及び遊牧国家と中華帝国の関係を理解するために、必要な資料を選択、読み取り、分析し、考察に利用することができる。
【資料活用の技能】 - 中央ユーラシア世界の遊牧国家の動向、オアシス都市をめぐる遊牧国家と中華帝国の抗争についての基本的知識を現代の国際関係と関連付けて身に付けている。
【知識・理解】
展開
全6時間
第1次 中央ユーラシア世界の遊牧国家、オアシス都市の形成の過程について基本的知識を身に付ける。(1時間)
第2次 課題解決のため、小テーマについて学習する際、適切な資料を選択、分析し、学習内容に関する理解を深める。(2時間)
第3次 課題解決に向け、分析した資料の内容を様々な側面、関連や変化、複数の角度などから考察し、考察した内容を発表、記述する。(3時間)[本時1/3]
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
- 遊牧騎馬民族国家とオアシス都市の形成過程や、中央ユーラシア世界と東アジア世界の関係について、資料を読み取った内容を基に根拠をもって他者と意見交換し、学習テーマについての考えをグループ内で統合することができる。
授業場面より
-
① 本時の見通しを持つ

「なぜ、中央ユーラシア世界は、古代も現在も中国との関係が密接なのか」という単元を通しての学習テーマと前時までに考察した「なぜ、古代の中国王朝はたびたびオアシス地帯に進出したのか」「なぜ、遊牧騎馬民族は古代中国王朝と対立を続けたのか」という小テーマを改めて確認することで、生徒は、今まで考察してきた問いと問いの関係に気付いていきます。教師は、あわせて本時の学習の流れや次回の授業で班ごとに発表をすることを伝えます。さらに、「多面的・多角的視点」「論理性」「知識・理解」「表現」の4点で評価をすること、それぞれどのような状態が望ましいかを問いかけながら伝えます。生徒はこれまでの単元でどのような説明や記述をしたか思い出したり、要所で頷いたりしていました。プロセスやゴールを確認することで、生徒は単元全体における本時の位置付け、何について考察し、どのようにまとめていけばよいかが明確になり、見通しを持つことができました。
-
② 語句を分類する
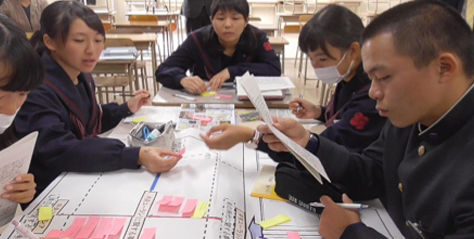
生徒は、前時までに学んだことを生かし語句を付箋紙に記入していきます。教師は、後で構造化しやすいように中央ユーラシアに関する語句は赤色、違う地域や立場の人に関する語句は黄色の付箋紙に書くように促します。あわせて「張騫の報告」(中国なので黄色)など書き方を例示します。そうすることで、生徒は中央ユーラシアかそうでないかを意識しながら、課題に答えるために必要な語句を多く付箋紙に記入することができました。
「ソグド人って何?」「オアシス都市で交易した人」「オアシス都市なら中央ユーラシアになるね」「ソグド人は金や宝石で身を飾っていたって」「交易を行っていたから、ソグド人は裕福だったのか」・・・生徒は、知識が不確かな場合は補足し合いながら、付箋紙を分類していきます。教師は、生徒が中央ユーラシア世界を多面的に捉えるとともに推移や他地域との関係を意識して考察できるようなシートを準備していました。生徒はこのシートを手掛かりにグループで協議することで、中央ユーラシアに関する語句を政治、経済、文化(宗教)、生活・社会に分類するとともに、単元で扱う前後の時代や東アジアや西アジア等他地域に関する語句を分類することができました。 -
③ 語句を関連付ける
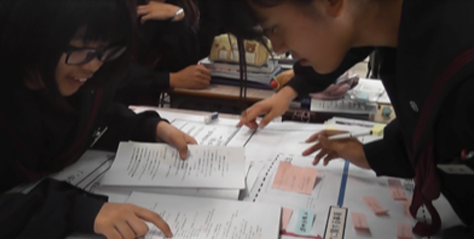
「どうまとめようかな・・・」「中央ユーラシアはオアシス系と遊牧系の民族に分かれるみたい」「中国も含め三者の関わりを見ていこう」「ソグド人は中国とも交易しているよ」「張騫もこれと関わりがあるね」・・・生徒は、分類した語句と語句を関連付けていきます。教師は、活動に入る前に、図示して関連付ける方法を示しました。その際に、以前の単元で生徒が作成したシートを例に、円で囲むだけではなくタイトルを付けると分かりやすい、矢印等でつないだ意図や意味を再度検討するとよいといったことを紹介します。そうすることで、生徒は関連付けをする最中に、語句と語句がどのようにつながるのか意識でき、迷った時は相談しながら再度付箋紙を操作したり、根拠となる資料等を読み直したりして吟味する姿が見られました。この活動により、因果関係など、曖昧だった語句と語句のつながりが分かるようになり、中央ユーラシア世界と周辺地域に関する知識が構造化され、他班に伝える内容がまとまっていきました。
-
④ 次時に行う発表の準備をする

教師は、次時の発表が充実するよう、語句の関連付けを行いながら、準備を進めるように促します。その際、発表時間(3分程度)、発表方法(プレゼン資料を使用)を伝えるとともに、再度評価項目を一緒に確認します。そうすることで、生徒は、今まで構造化を図ってきた内容をどのようにまとめて発表していくか考え始めました。班内では、内容を絞り込むためにさらに協議をする人、パソコンを使ってプレゼン資料を作成する人と役割分担をして準備に向いました。ある生徒が、「発表したい内容が多すぎて時間内に収まりそうにない・・・」と不安そうにつぶやきました。すると教師が「問いに対する答えになっているかを意識して焦点化してみては?発表では『〇〇の部分に注目して発表します』という方法もあるよ」と助言をしました。助言を受けた生徒は、「交易など経済的なつながりは絶対外せないね。ここから考えよう」と発言し、シートを基に班員とさらに協議を進めていきました。終礼が鳴った後も多くの班が、何をどこまで伝えるか、どのような構成にするか協議を続けていました。次の時間に行う発表に向けて、粘り強く学習課題に向き合う姿が見られました。
報告者:研修協力員 山本

