アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:岐阜市立陽南中学校
教科等:1年数学科(平成29年10月)
単元名:比例と反比例
数理的に考察する力を育成したい
 興味や関心を高める
興味や関心を高める 互いの考えを比較する
互いの考えを比較する 知識・技能を活用する
知識・技能を活用する
実践の背景
- 当校は、「課題に向かって、主体的に学習に取り組む生徒」「ねばり強く、心身を鍛える生徒」「思いやりの心をもって、仲間と協力できる生徒」を学校の教育目標に掲げ、学び合いを通して、学びの深まりを実感する生徒を育てています。
- 生徒一人ひとりに「学びがいが実感できる」をキーワードに、『生きる力』を育むための教育課程のもとで実践を重ね研究を進めています。
- 学校の教育目標等を踏まえ、研究主題を「自立した学びを実現する生徒の育成」とし、「主体性を育む」ことを前提として、新学習指導要領が示す「生きる力の育成」を目指して、実践に取り組んでいます。
授業改善のアプローチ
- 事象から数学的な側面を捉え、解決方法を見通す導入の工夫
- 思考の過程を明らかにするための学習過程の在り方
- 自己の学びを認識し、数学的な見方や考え方のよさを味わわせる振り返りの在り方
単元づくりのポイント
目標
- 様々な事象を比例、反比例などでとらえたり、表、式、グラフなどで表したりするなど、数学的に考え表現することに関心をもち、意欲的に数学を問題の解決に活用して考えたり判断したりしようとしている。
【数学への関心・意欲・態度】 - 比例、反比例などについての基礎的・基本的な知識や技能を活用して、論理的に考察し表現するなど、数学的な見方や考え方を身に付けている。
【数学的な見方や考え方】 - 比例、反比例などの関数関係を、表、式、グラフなどを用いて的確に表現したり、数学的に処理したりするなどの技能を身に付けている。
【数学的な技能】 - 関数関係の意味、比例や反比例の意味、比例や反比例の関係を表す表、式、グラフの特徴などを理解し、知識を身に付けている。
【数量や図形についての知識・理解】
展開
1 関数
ともなって変わる2つの数量の関係を、表や式、グラフを使って調べ、その有用性を理解する。
第1時:2つの数量の関係の調べ方
第2時:ともなって変わる2つの量
2 比例
比例の関係について、その変化や対応のようすを調べ、表や式、グラフで捉えながら理解する。
第3-4時:比例
第5時:座標
第6-7時:比例のグラフ
第8時:比例のグラフのかき方
第9時:比例の式の求め方
3 反比例
反比例の関係について、その変化や対応のようすを調べ、表や式、グラフで捉えながら理解する。
第10時:反比例
第11-12時:反比例のグラフ
第13時:反比例の式の求め方
4 比例、反比例の利用
身のまわりの問題を、比例や反比例の関係に着目し、表や式、グラフを利用して解決する。
第14時:身のまわりの問題への利用
第15時:図形への利用
第16時:活用の問題
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
脈拍を一定数数えたときの時間とめもりの値の関係を調べる活動を通して、表、グラフに表せば二つの数量の変化や対応についての特徴を明らかにできることに気付き、二つの数量の関係が反比例であることを説明できる。
授業場面より
-
①身のまわりから問いを見いだす

「先生は、自分の脈拍を15回数えただけで、なぜ1分間の脈拍数が分かったのだろう」と、生徒から疑問の声があがります。
教師がナースウォッチを示し、その文字盤のめもりを見て調べたことに気付きました。しかし、脈拍数と時間の関係が分かりません。そこで、この関係性を明らかにしていくことが本時のねらいとなりました。
このようにして、生徒が抱いた疑問を生かして学習課題を生み出していきます。
ここには、身のまわりと数学をつなぐ具体的な事象提示によって、学ぶ意義を生徒が味わうことができるようにする教師の意図があります。 -
②既習を活用して考える

「脈拍を15回数えたときの秒数が1秒で・・・でも、60秒で900回っておかしいな。」
文字盤のめもりに着目し、既習を生かしてナースウォッチから読み取ったことを表にしたり、グラフに表したりします。そこから、数量の感覚を働かせつつ、自分の考えを導き出していきます。
このように、自力解決の場を保障することで、自分に解決できることと未だ分からないことの自覚を促し、さらには、仲間と議論する必然を生み出していきます。 -
③議論を通して考えを広げ深める
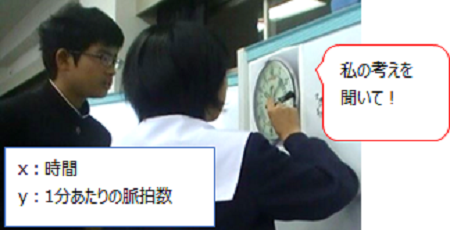
「ナースウォッチのめもりは、秒数が増えるにつれ脈拍数が減っているから、反比例に見えるね。」「表にしてみたら、y=a/xの関係が成り立っていることが分かった。」「グラフを作ってみて、双曲線になればいいよね。」と、グループの仲間から、自分と共通した考えや自分にはなかった考えを聴きます。
そこには、立型で大きめのホワイトボードによって、他者と容易く情報を共有でき、考えを広げたり深めたりできる良さがあります。 -
④他者に考えを説明する
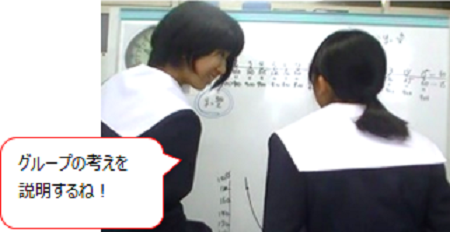
「ナースウォッチのめもりを読み取ると、15秒の時では脈拍数が60回、10秒で90回・・・だったから、それぞれの値をxとyにして式で表すと、y=900/xになりました。これは反比例の関係にあると言えそうです。」「私のグループでは、グラフで同じことが説明できたよ。」
このように、グループで深めた考えを他者と説明し合います。このことによって、少しずつ自分の考えに自信を持つようになります。
この生徒は、「相手に説明し、理解してもらえることで、自分の考えがはっきりとしてきました。」と振り返ります。
報告者:研修協力員 各務

