アクティブ・ラーニング授業実践事例
学校名:長野県諏訪清陵高等学校附属中学校
教科等:2年外国語科(平成29年6月)
単元名:ボクらの時代~紹介しよう!大好きな人・憧れの人・尊敬する人~
話すことに重点を置いた英語によるコミュニケーション能力を育成したい
 見通しを持つ
見通しを持つ 協働して課題解決する
協働して課題解決する 知識・技能を活用する
知識・技能を活用する
実践の背景
- 実践校は開校して4年目の中高一貫校です。適性検査を経て入学する生徒は学習意欲も高く知識も豊富です。そんな生徒に「本物の実力」を付けるため、中高教員が連携して6年間を見据えた学校づくりをしています。
- 65分の豊富な授業時間を生かし、習得させるべきことを徹底し、考えさせるべきことはじっくりと考えられるような授業づくりを行っています。また、予習・復習にも重点を置き、授業と家庭学習の関連を図っています。
- 本年度より公開研究会を実施し、各教科で「本時の授業のみどころ」を参観者に配布しています。以下のポイントを記述することで、全教員が同じ視点で学びをデザインできるように工夫しています。
① 単元全体における本時の位置(学習問題の深まり)
② 本時に至る学びの姿(前時までの生徒の学び、予備学習として課した家庭学習の内容)
③ 本時の学習過程(本時の学習問題と学習過程、生徒の意識の流れなど)
④ 本時、実現したい学びの姿(ゴールイメージとして描く生徒の姿)
⑤ 「ここに注目!」(参観者に見取っていただきたい生徒の学びの姿)
⑥ 「ここを聞かせて!」(参観者に語っていただきたい授業改善に関する成果や課題等)
授業改善のアプローチ
- 生徒の「心の声」を受け止めて研究をスタートする(英語科教科会を例に)
「わたしは『使える』英語を学びたい」。イングリッシュキャンプ後の集会である生徒が発した一言です。生徒はホストファミリーとの団らんで自分の伝えたい思いを表現できないもどかしさを感じていました。英語科教科会では、この一言を生徒全体の「声」として受け止めて授業改善をスタートしました。
*「イングリッシュキャンプ」・・・異文化理解の深化に加え、学校で学んだ英語の実践的な活用の機会を求めて、2年生全員がアメリカ人家庭に数名ずつホームステイする活動。
- 教科会で協働的に単元をデザインする(英語科教科会を例に)
・「話すことに重点を置いた英語によるコミュニケーション能力の育成」を研究テーマとし、本年度は英語科の教員全員で協働的に単元をデザインしています。
・単元デザインでは、特に習得した知識や技能を活用する学習活動をどのように生成するかがポイントとなります。本校では生徒が学びたいことと教師の教えたいことが合致する学習活動を生み出せるように、両者のバランスを大事に考えながら学習活動を考えています。
単元づくりのポイント
目標
- つなぎ言葉や話題転換の言葉を使うなど、自分の知っている英語を総動員してコミュニケーションを続けようとしている。
(主体的に学習に取り組む態度) - 1学期前半(Lesson1~3)に学んだ既習の語や連語及び慣用表現、文法事項を用いて的確に表現することができる。
(知識及び技能) - 紹介する人物の情報をアイディアマップに整理して簡単な語句やキーワードを用いて伝えたり、質問に答えたりすることができる。
(思考力、判断力、表現力等)
展開
- 本単元は、1学期前半に学んできた知識や技能を複合的に活用する機会として位置付けました。
- 例えば、4月から6月(Lesson1からLesson3)までに以下のような学習をしてきました。
・Lesson1 過去形〈一般動詞〉(1年生の復習)
・Lesson2 過去形〈be動詞〉(肯定・疑問・否定)/過去進行形/接続詞 when
・Lesson3 未来を表す表現(will , be going to)/接続詞 that
- 展開の概要は以下の通りです。
第1時:紹介したい人物(大好きな人・憧れの人・尊敬する人)のアイディアマップを作成しよう!
第2時:相手と会話がつながるための疑問文を考えよう!(ボクらの時代①)
第3時:始まるよ!「ボクらの時代②」 ~自然な対話を目指してみよう!~ 【本時】
第4時:録画放送!「ボクらの時代③」 ~録画を見て課題をつかもう!~
第5時:生放送!「ボクらの時代④」 ~別クラスと対談にチャレンジ!~
「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善
本時のねらい
「大好きな人・憧れの人・尊敬する人」をテーマとした2回目の対談を振り返る場面で、対談の録音データを聞き取り、対談前に使おうとしていた既習の語や連語等の活用状況を確かめ、再度対談に挑戦することを通して、自然なコミュニケーション実現のために使える英語表現を増やすことができる。
授業場面より
-
①自然な対談を目指そう!

まずはWarm-Upとして生徒同士で既習の英単語や英熟語の問題を出し合い、教師はクイズ形式でさらに問題を出しました。英語を楽しく学ぶ雰囲気が生まれ、生徒の意欲も高まります。次に、教師は前時に行った初めての対談の感想を尋ねました。「Ohばかりになっちゃった」「会話が続かなかった」という複数の生徒の発言を全体で共有し、「今日は自然な対談を目指そう!」というToday's Goalが設定されました。
-
②こうすれば自然な対談になりそうだ
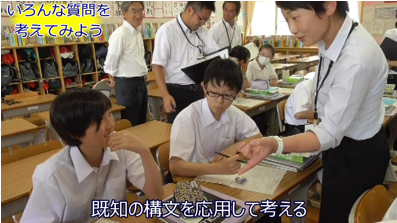
次に自然な対談にするためのポイントとして、会話のテンポ、ジェスチャーなどの有効性を確認しました。また、「質問が難しかった」という悩みに対して、尋ねたい疑問文を考えるように促したり、時制・助動詞・連語・話題転換・接続詞などの「これだけは使いたい表現」シートに蛍光ペンで線を引くように促したりしました。このような教師の関わりによって、生徒は自然な対談を実現するために課題解決の見通しを持ちました。
-
③なかなかうまくいかないなあ・・・

2回目の対談のメンバーが発表され、5分間の対談が始まりました。生徒が英語で紹介する「大好きな人・憧れの人・尊敬する人」はバラエティーに富んでいました。仲間が紹介する人物をもっと知るために、「これだけは使いたい表現」シートを参考として質問を重ねましたが、なかなかうまくいきません。対談後、視聴者役のグループから改善点を聞いたり、対談の録音データを聞き取ったりすることで、協働的に課題解決を図りました。
-
④前回よりも自然な対談になったよ!
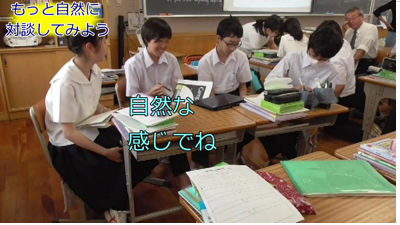
このグループでは「By the wayで話を切るのではなく、質問をして話題を深めたい」という新たな課題を持ちました。同じグループで取り組んだ2回目の対談では、友達が尊敬する歌手を紹介した瞬間、"Oh! I know. I like Dragon Night."とリアクションしたことで、友達から"Me,too"という自然な答えを導き出しました。本時の学びを振り返る場面では、前時よりも自然な対談に近づけたことを自覚することができました。
報告者:研修協力員 谷内

