NITSインタビュー ~学びのスパイス~
第2回 島谷千春審議役[後編]
独立行政法人教職員支援機構(以下、NITS)では、役職員や教育関係者へのインタビューを通して、教育に関わる知見を広く提供するとともに、より多くの教職員や教職員を目指すみなさんに、NITSについて知り、関心を持っていただくことで、日々のちょっとしたスパイスになればとの想いから、「NITSインタビュー ~学びのスパイス~」を行っています。
第2回は、NITSの島谷千春審議役です。前・後編の2回に分けてお届けします。今回はその後編です。
- 前編はこちらからお読みいただけます。
――教育長時代の映像を拝見して、NITSに赴任された今もそうですが、本当にエネルギッシュですよね。その原動力は何なのでしょうか?
もともと、登れるものは全部登ろうとするようなよく動く子供でした。体のコンディションを整えたりよく寝たり、健康面への気遣いは最低ラインとして、気持ち面では、毎月ワークをやるようにしています。
――ワークってどんなものですか?
毎月、目標とか頑張ることとか行きたい場所とかを書くスペースのある手帳を使っています。現状把握や目標を達成するために何をすべきかなど、自分と向き合う時間をできるだけ取るように心がけていて、それをもとに具体に行動することを決めるようにしています。都度迷うのが面倒くさいというのもありますが。ワークをすると、頭の中で散らかっていることが整理できるんです。何となくふわふわと考えていることを文字化して着地させると、物事のつながりとか、やるべきことが見えてくるんですよね。
例えば今、地域版マネプロ(研修マネジメント力協働開発プログラム(地域版))で全国各地を飛び回っていて、結構大変です。でも、全国の様子を一通り見ないと、地域の様子が分からず、方向性の感覚が持てないし、次年度以降の制度設計はできません。なので、「とにかく全部行く」とワークに書いて、実行しています。辛いけど(笑)。
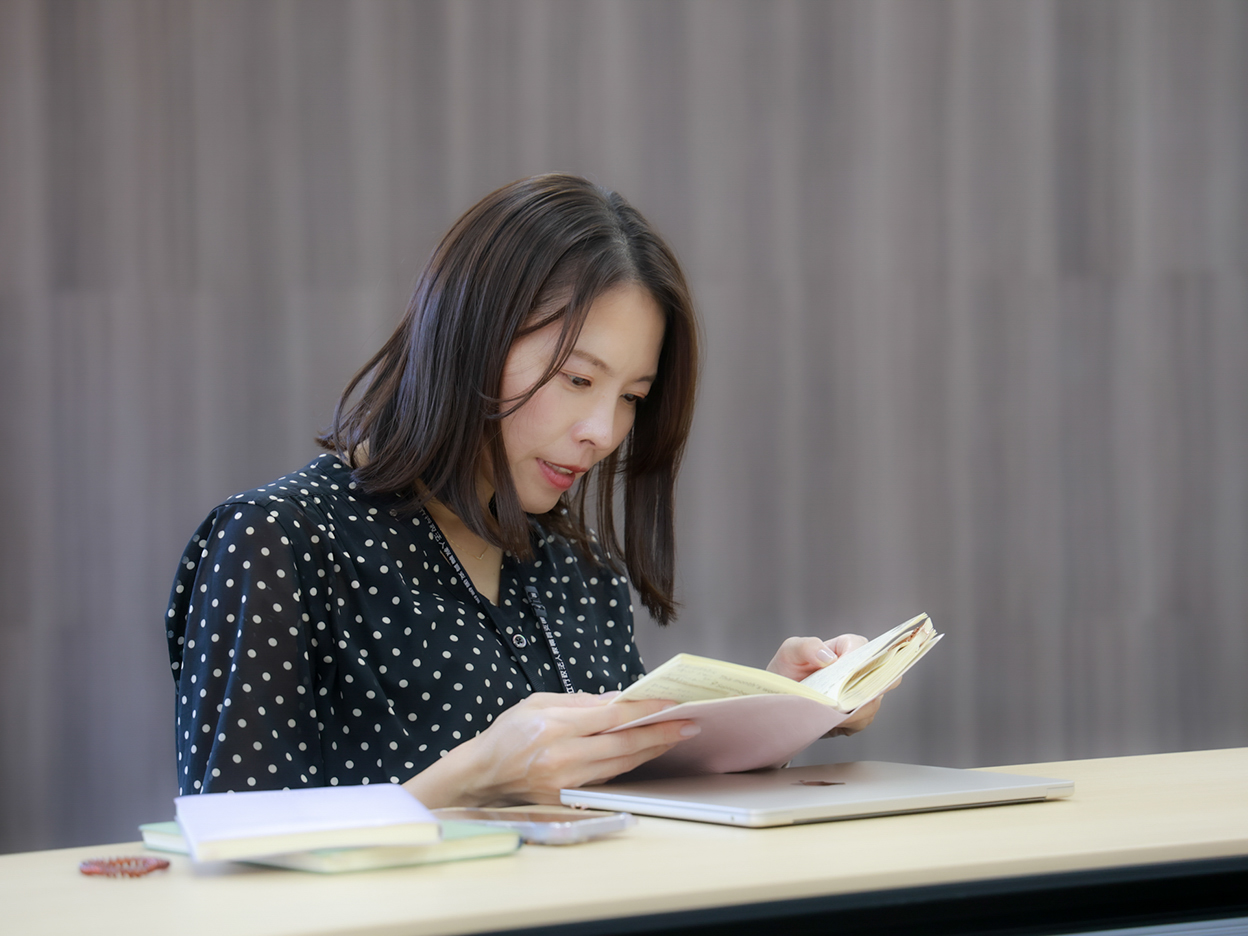
――いつ頃から始められたんですか?
教育長時代からです。リーダーという立場になり、自分が決めることが増えたので。どうしようかなと考えていると、あっという間に時間は過ぎていってしまいます。文部科学省で勤務していた時は、上から下りてきたり、外から働きかけられたり、他律的な要素も大きかったのですが、教育長は自分で決めないと物事が動きません。だから、自信を持って決めて、進むために、自分としっかり向き合うことができるワークが必要不可欠になりました。
――他にはどんなことが書いてあるんですか?
年度初めの4月なら、「新しく出会った人たちと丁寧に接する」「とにかく人の話を聴く」など。仕事関係のことだけでなく、「断捨離する」とか「必ずライブの抽選に応募する」とかもあります。いつかやろう、やりたいなと思っていても、その「いつか」は来ないので、すぐに予定を立てるんです。そして、書いたけど実現できなかったことは、必ずリベンジして実現できるようにしています。やりたいことがたくさんあるんですが、いつ死んでも後悔しないように。
最近だと、夏休みにサップ(SUP:Stand Up Paddle)をしに福岡に行く予定を立てていたのですが、台風の影響で行けなくなってしまって。でも、「すぐに必ず行く!」と書いて予定を立てて、9月にリベンジしに行ってきました!
――アクティブですね!ライブのお話もありましたが、音楽がお好きなんですか?
Official髭男dismの大ファンで、音楽を聴いて気持ちを盛り上げています。考えてみたら、仕事以外ではずっと音楽が流れているかもしれません。時間帯によって雰囲気を変えていて、夜はしっとりジャズ、朝は元気にYOASOBI(笑)。家事も子育ても大忙しなので、音楽を聴いたりして、意識的に自分と向き合う時間を作り、立ち位置を自覚するようにしています。

――ワーク・ライフ・バランスはどのようにとっていますか?
「今、私バランスがとれている!」と思ったことは、今まで一度もありませんね。どうしてもウエイトが仕事に寄りがちなので、家事は愛だと思って「量より質」で勝負しています(笑)。週末にお惣菜を作り置きしたり、平日は朝4時半に起きてお弁当を作ったりしています。
あとは、つくばまでの通勤時間が長いので、その時間を活用して本を読んでいます。オンオフを切り替えるために、小説に没入することも楽しみの一つですし、私は教育関係のものより、デザインや広報、行動経済など、人の気持ちや行動に関するものをよく読んでいます。他の分野に触れるのはとても大事だと思っているので。他分野といえども、教育とどこかで通底する部分があると、納得感も倍増します。
――NITSに赴任が決まった時、どう思いましたか?
文部科学省では、教育のほか科学技術や国際関係など本当にさまざまな業務を扱っているので、異動すると転職したかと思うくらいの異動もあります。それに比べたら、教育委員会からNITSへの異動は学校教育という共通分野を扱う組織なので、マイルドな変化でした。あと、引き続き現場の先生たちと接することができる仕事であることはうれしかったですね。NITSが進めている「子供の学びと教師の学びは相似形」は、教育長の頃から実感しながら進めてきたので。異動に驚かれることも多かったですが、私のことやNITSをよく知る人からは「ぴったりだね」とも言ってもらえました。
――NITSでは、役員の次席である「審議役」という役職に就任されました。
自由度が大きいので、良くも悪くもその人次第の役職だと思っています。これまで私は引継どおりに仕事をしたことがなくて、ポストを作り替えちゃうタイプ(笑)。でも、そもそも組織として、10年間全く同じ仕事が続くポストなんて有り得ないじゃないですか。役職が何であれ、その時に必要なことを、よりよくするために仕事をするというスタンスは変わりません。でも、教育長時代と違って自分が一番上ではないので、正直気持ちは軽いです。
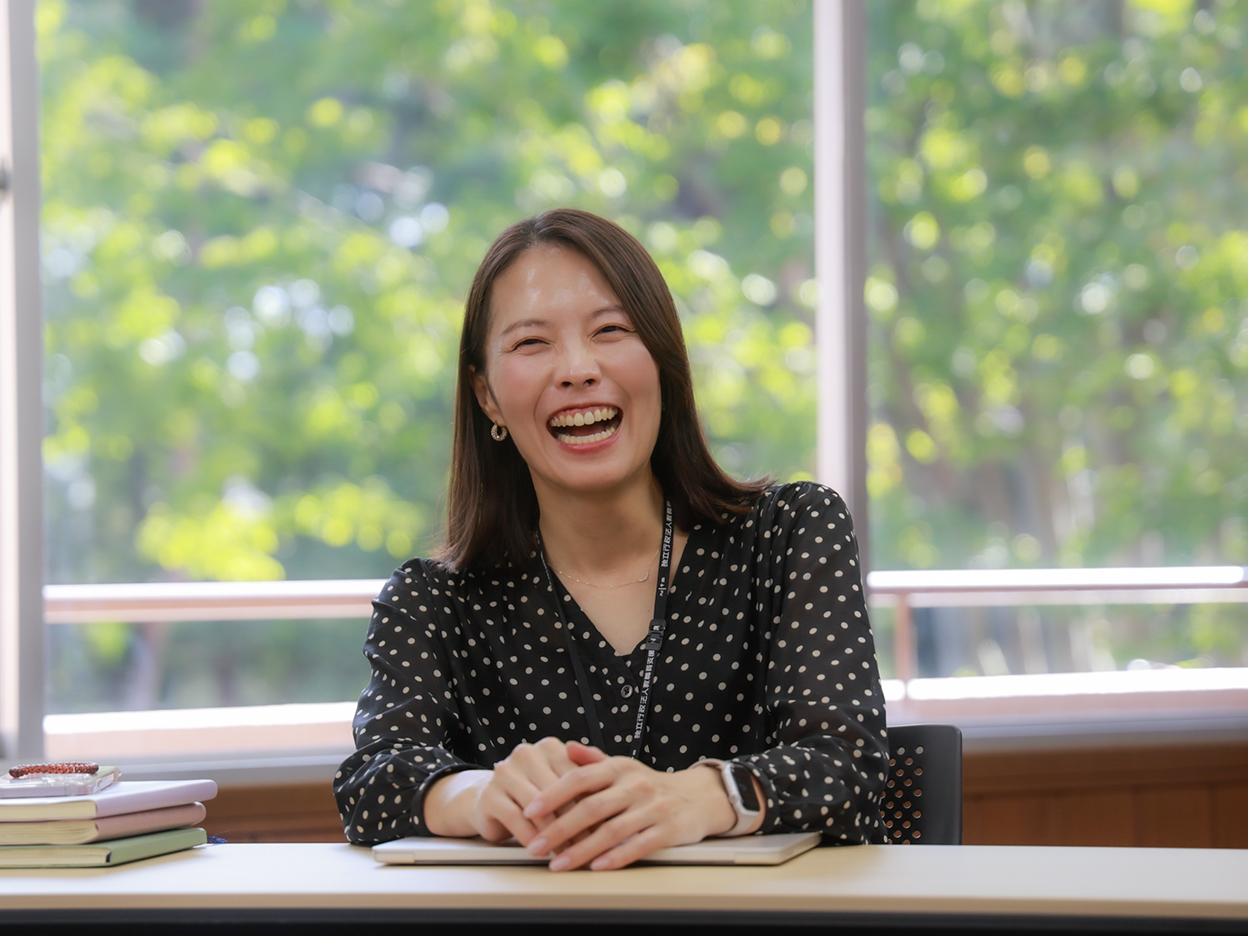
――NITSにいらして、およそ半年が過ぎました。これからの目標を教えてください。
今のNITSの使命は、子供の学びの転換を進めるために、それを支える全国の先生たちの学びを変えていくことであり、「研修観の転換」を進めていくことです。でも私自身、正直まだこの「研修観の転換」の正体がよく分からなかったりします。チームで研修をゼロから作っては、失敗も出てきて。それを修正しにいってまた新たな経験を積み重ねながら、暗黙知が形式知に変わっていったりと、行きつ戻りつしながら進んでいます。大事なのは、そういう「試行錯誤」をやめないこと、考え続けること、仲間を増やすことだと思っています。こういうことを、全国の研修センターの皆さんや、校内研修を支えている先生たちと一緒にみんなで考えて、チャレンジして、そして確実に「何か行動していく」、そういう風がびゅんびゅん吹いていくように頑張っていこうと思います。
――NITS全体で、そんな風を起こしていけたらよいですね。本日は、ありがとうございました。

